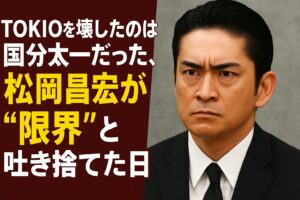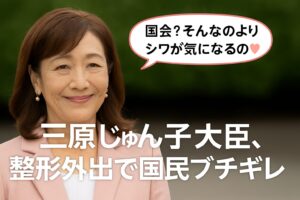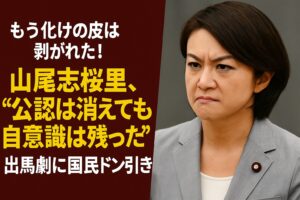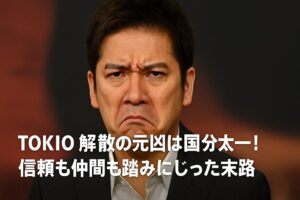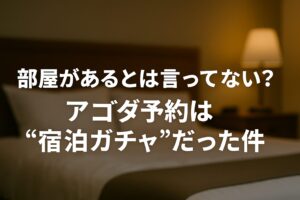「え、ココイチのカレーが1食2000円!?」
そんな驚きの声を、最近あちこちで耳にするようになりました。ネット上でも、街のあちこちでも、“ウーバー価格”になったカレーに戸惑う人が増えているようです。
かつては、学生のお腹を満たしてくれる庶民派チェーンだったココイチ(カレーハウスCoCo壱番屋)。筆者も学生時代は、ワンコインでお釣りがくるシンプルなポークカレーに、何度も助けられた記憶があります。でも今では、同じココイチのカレーをウーバーイーツで頼むと、配達料やサービス料が加わって、1食2000円を超えるケースも珍しくありません。
気がつけば、「たまの贅沢」「セレブの食事」と言われるような存在に変わってきたのです。
もちろん、物価が上がっているのはココイチだけではありません。統計的にも、ここ数年で食料品やサービス価格は1.5倍近くに跳ね上がっているとされています。その一方で、平均賃金はほとんど横ばい。家計の余裕が増えない中での値上げは、想像以上に日々の暮らしに影響を及ぼしています。
では、こうした「高すぎる」と感じる感覚の裏側には、何があるのでしょうか?
この記事では、筆者自身がウーバーイーツの配達員として体験したリアルな現場の声と、経済ジャーナリストとしての視点を交えながら、ココイチ離れが進む理由や、デリバリーを「贅沢」と感じる庶民感覚の背景を、できるだけわかりやすくお伝えしていきます。
ウーバーでココイチ1食2000円超え!? 「もはやセレブ食」と言われる現実と、庶民が感じるギャップ

「カレー1杯が2000円って、もはや外食というより“ちょっとした贅沢”ですよね。」最近、こんな声を耳にすることが増えてきました。
特にフードデリバリーをよく使う人にとっては、これはまさに現実の話。以前は手頃な価格で食べられたはずのカレーも、今では「高くて頼めない」と感じる人が少なくありません。
たとえば、かつて学生の定番だった「カレーハウスココイチ(CoCo壱番屋)」。ボリュームのあるロースカツカレーが人気で、「安くてガッツリ食べられる」という印象を持っていた方も多いと思います。ところが、ウーバーイーツなどのフードデリバリーで注文すると、配達料やサービス料がかさみ、気がつけば2000円を超えていることも珍しくないんです。
もちろん、「たかがカレー、されどカレー」。食の楽しみ方が多様化する中で、多少高くても“好きな味を自宅で楽しめる”という価値を感じる人もいます。でも、それでもやっぱり「ちょっと高すぎない?」という感覚、正直なところ、多くの人が抱えているのではないでしょうか。
背景には、急速に進んでいる物価の上昇があります。食材価格はもちろん、人件費や物流コスト、エネルギー価格の高騰など、あらゆるコストが企業の肩にのしかかっています。それが商品価格やサービス料に反映され、結果として消費者が支払う金額が跳ね上がっているのです。
ところが一方で、日本人の約8割が「給料は上がっていない」と感じているのも現実です。実際、厚生労働省の統計などを見ても、物価の上昇に対して賃金の伸びが追いついていないことがはっきりとわかります。生活の実感として「ちょっとした買い物が以前よりずっと高く感じる」という人も増えていますよね。
こうした「価格が上がる一方で、収入が伸びない」というギャップは、家計にも心理的にもじわじわと負担を与えています。フードデリバリーは便利ですが、それを日常的に利用するには、もはや相応の“経済的余裕”が必要な時代に入ったのかもしれません。
今後、私たちはどう向き合っていけばよいのか。
便利さを手放すのか、支出のバランスを見直すのか。それとも、もう一歩踏み込んで、経済全体の流れをどう変えるべきかを考えるべき時期に来ているのか。デリバリーカレー1杯の値段は、そんな大きな問いを私たちに投げかけているのかもしれません。
価格は1.5倍、でも給料は据え置き。広がる“生活実感”とのズレ

ココイチの定番メニュー、ロースカツカレー。店舗で食べると998円です。もちろん、決して安いとは言えませんが、それでも「たまにはいいか」と思える価格帯ではありますよね。
とはいえ、昔を知っている人にとっては、やっぱり「高くなったなあ」と感じるのも自然なことだと思います。
筆者自身、独身時代(30年前かな)はというと、もっとシンプルなポークカレー(当時430円)ばかりを頼んでいました。まさに“財布の味方”。ワンコインでお釣りがくるというだけで、安心して通えていた記憶があります。あの頃の物価や生活感と比べると、今の価格設定には、少しだけ距離を感じてしまうのも無理はありません。
ところが、もしこのロースカツカレーをウーバーイーツなどのフードデリバリーで頼もうとすると、話は一気に変わります。配達料やサービス料が加わることで、最終的な支払額が2000円を超えてしまうケースが普通にあるんです。
もちろん、デリバリーは「待っていれば家に届く」という圧倒的な便利さがあります。仕事帰りで疲れているときや、外に出たくない雨の日には、ありがたい存在であることは間違いありません。でも、2000円という価格を目の前にすると、「さすがに高すぎない?」と、ためらってしまう人も多いはずです。正直なところ、筆者も思わずアプリを閉じてしまった経験があります。
これはもはや「外食」というより、ちょっとした“セレブ食”。誰でも気軽に頼める時代は終わりつつあるのかもしれません。
では、なぜここまで価格が高く感じられるのでしょうか。その背景には、日本の平均賃金の伸び悩みという深刻な問題があります。実はこの10年間、日本の賃金はほとんど上がっていません。国際的に見てもその傾向は顕著で、OECD(経済協力開発機構)に加盟する先進国の中でも、日本の賃金上昇率はほぼ最下位クラスにとどまっています。
つまり、支出はどんどん増えているのに、収入はそのまま。感覚として「すべてのものが高くなった」という印象だけが強く残り、買い物や外食、そしてフードデリバリーのたびに「贅沢しちゃったな…」と罪悪感を感じてしまう。そんな空気が、じわじわと日常を覆い始めています。
結局のところ、「たまにはデリバリーで楽をしたい」と思う気持ちと、「2000円はさすがに出せない」という現実のはざまで、多くの人が葛藤しているのではないでしょうか。「自分で取りに行った方がマシ」「外食より自炊」といった選択が増えているのも、単なる節約志向というより、“収入に見合わない価格”への抵抗感とも言えそうです。
この状況を放置すれば、「便利なサービス=限られた人の特権」となり、生活の格差をさらに広げることにもなりかねません。価格の問題だけではなく、私たちがこの“価格と価値のズレ”をどう受け止め、どう暮らしを調整していくかが、今後ますます問われていく時代に入ってきたのかもしれません。
フードデリバリー=“時間を買う”選択。でも誰もが買えるわけじゃない

ウーバーイーツでココイチを注文する人たちには、ある共通点があります。
それは、一人暮らしやDINKS(共働き・子どもなし)といった、比較的少人数で暮らす世帯が多いということ。中には、高級マンションや都市郊外の戸建てに住んでいるような層も見られます。
つまり、ある程度の可処分所得(自由に使えるお金)を持っている人たちが、時間と手間をお金で買っているというのが、現在のフードデリバリーのリアルな利用構図です。仕事が忙しい平日、自炊する余裕がないとき、あるいは休日にゆっくり過ごしたいとき「わざわざ出かけずに、家で好きなものを食べたい」というニーズを満たすために、多少高くてもデリバリーを選ぶ。そこには、“利便性にお金を払う”という価値観がしっかりと根付いています。
一方で、現実にはまったく違う立場にある人たちも増えています。物価が上がり続ける中、日々の生活費を切り詰めながら暮らす世帯にとっては、月に一度の外食ですら「ちょっと贅沢」と感じられるようになってきました。ましてや、ウーバーイーツで一食2000円超のカレーを注文するというのは、もはや“非現実的”な選択肢なのです。
このようにして、「何を、どう食べるか」が、その人の暮らしの余裕や経済状態を如実に表す時代になりつつあります。かつては「食事は平等だ」と言われることもありましたが、今はどうでしょう。スーパーで値引きされた総菜を選ぶか、アプリで高額なデリバリーを迷いなく頼むか。その選択の背景には、明確な“生活の格差”が存在しています。
特に都市部では、この差がより顕著です。街を歩けば、カフェでブランチを楽しむ若者がいる一方で、コンビニで100円のパンを迷いながら手に取る高齢者の姿もあります。同じ空の下、同じ時間に、まったく異なる食の風景が並んでいる、それが今の日本の現実です。
この「日常の食事が“格差”を映す」という構図は、単なる個人の選択ではなく、社会全体の構造的な歪みを反映しています。可処分所得が増えず、物価ばかりが上がる。しかもその影響は、日々の暮らしの中で最も基本的な「食」にまで及んでいるのです。
本来、食事は誰にとっても安心できるものであり、楽しみであるべきはずです。それが今や、「どこで何を食べるか」が階層を分ける指標のようになってしまっている。この事実をどう受け止め、どう変えていくかは、個人の問題ではなく、社会全体で考えるべき問いだと思います。
たった一杯のデリバリーカレーが、私たちの暮らしの現在地と、これからの方向性を静かに物語っているのかもしれません。
外食産業の値上げは「悪」じゃない。でも“庶民の実感”から乖離すれば離れていく

「値上げ=悪」と単純に決めつけることはできません。
むしろ今の時代、外食産業をはじめ多くのサービス業が、原材料費や人件費、電気代などの高騰に直面しており、価格を見直さざるを得ない状況が続いています。それはもう、「値上げは悪か?」という問い以前に、「これ以上、どうやってコストを吸収するのか?」という現場の切実な声が背景にあるのです。
フードデリバリーに関しても同様です。私たちはつい、「高いなあ」と感じてしまいがちですが、冷静に考えれば、その価格には配達員への報酬やアプリのシステム維持費など、見えないコストがいくつも含まれています。時間帯によっては自転車やバイクで何キロも移動してくれる配達員の労力、注文を処理し続けるアプリの運営体制。どれも“無料”ではありませんし、簡単に削れるものでもありません。
実際、筆者もウーバーイーツでココイチを注文してみたことがあります。正直、注文ボタンを押すときは「ちょっと高いな」と思いました。でも、届いたカレーは想像以上に熱々で、食欲をそそる香りが立ちのぼってきた瞬間、「ああ、頼んでよかったな」と素直に思いました。
口に運べば、変わらない美味しさがそこにあって、しかも自宅のリビングでくつろぎながら味わえる。スピードもクオリティも申し分なく、「たまにはこういう贅沢もアリだな」と感じたのは確かです。
でも、そう感じられるのは、“心にも財布にも余裕があるとき”に限られます。冷静に考えれば、一食2000円近くするカレーを頻繁に頼むのは、やはり現実的ではありません。家計に負担をかけずに生活したいと考える人にとって、フードデリバリーはすでに「日常的な選択肢」ではなく、「ときどきの特別なご褒美」になりつつあるのではないでしょうか。
そして、これは筆者一人の感想ではなく、多くの人が抱えている実感でもあるはずです。「便利なのはわかってる、でもちょっと高すぎる」。その感覚は、フードデリバリーに限らず、最近のあらゆる価格設定に対して共通して広がっているものだと感じます。
重要なのは、単に「高い・安い」で判断するのではなく、その価格に見合った“納得感”や“満足感”があるかどうか。そして、それを誰もが公平に享受できる社会なのかどうかを見つめ直すことなのではないでしょうか。
サービス提供者側の事情を理解しながらも、利用者側の声を無視しないこと。そこに、これからの社会が目指すべき“バランス”があるように思います。
まとめ:デリバリーが贅沢になる時代。問われるのは「価値の設計」

今や、ウーバーイーツで外食メニューを注文するという行為は、単なる“手抜き”や“時短”の手段ではなくなってきています。
むしろそれは、「今日はがんばったから」「たまには自分にご褒美を」というような、少しだけ背伸びをしたいときの特別な選択肢になりつつあるのが現実です。
一方で、そこには“便利さ”という恩恵と引き換えに、私たちが見過ごしていることもあるかもしれません。たとえば、手間を省く代わりに支払う金額の重み。あるいは、「この価格で本当に納得できるか?」と、無意識に感じている違和感。そのひとつひとつが、日々の選択の中で少しずつ蓄積されていきます。
デリバリーサービスがこれからも私たちの生活に根づいていくためには、単に「速く届く」「おいしい」というだけでなく、その価格に見合う、あるいはそれ以上の“体験価値”をいかに提供できるかが問われる時代に入っていると思います。
料理のクオリティはもちろん、サービスの丁寧さ、ストレスの少なさ、そして「頼んでよかった」と思える安心感。そうした細部に宿る満足感こそが、価格を超える価値として記憶に残るのではないでしょうか。
そして同時に、私たち消費者側にも問われていることがあります。
それは、「安いから買う」「高いから買わない」という単純な判断だけでなく、“その価格にはどんな価値が含まれているのか”を自分なりに見極める視点を持つことです。何を優先し、何を手放すのか——。その判断は、これからの生活においてますます重要になっていくはずです。
結局のところ、価格と価値のバランスに納得できるかどうか。そこに、私たちが何にお金と時間を費やし、どんな生活を望んでいるのかという、個人の選択の本質がにじみ出ているのかもしれません。